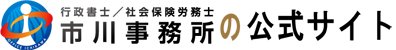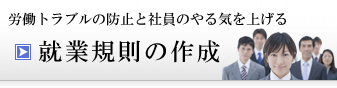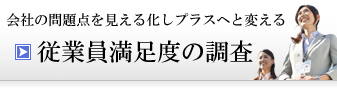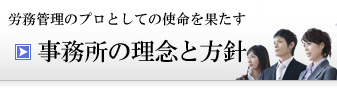1週間の法定労働時間が44時間になる業種は?
そして、週44時間制度が適用される条件は?
通常、1週間の法定労働時間は40時間ですが、下記の業種で常時使用する労働者(パート・アルバイトを含む。以下同じ。)が10名未満の事業場に関しては法定労働時間が週44時間となっています。
| 業種 | 該当するもの |
| 商業 | 卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、駐車場業、不動産管理業、出版業(印刷部門を除く。)その他の商業 |
| 映画・演劇業 | 映画の映写、演劇、その他興業の事業(映画製作・ビデオ製作の事業を除く。) |
| 保健衛生業 | 病院、診療所、保育園、老人ホーム等の社会福祉施設、浴場業(個室付き浴場業を除く。)、その他の保健衛生業 |
| 接客娯楽業 | 旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地、その他の接客娯楽業 |
週44時間というと、たった4時間しか変わらないので、「大したことない」と感じるかもしれませんが、実は残業代に非常に大きな差が出るんです。
給料が20万円の社員がいたとすると、週に44時間働いた場合、通常であれば残業代が2万6000円になります。
しかし、週44時間制が適用できる場合は・・・。
ナント!残業代が0円になるわけです。
これは、インチキでも何でもなく、法律に沿った正当な運用なのです。
活用できる所は活用しないともったいない制度です。
常時使用される労働者が10名未満とは?
この制度が適用される「常時使用される労働者が10人未満」とは具体的にどの労働者をカウントするのでしょうか?
社会保険や雇用保険、助成金申請などは、「この常時使用される労働者」について具体的な定めがあります。
しかし、困ったことに労働基準法では「常時使用される労働者」について具体的な定めが無く非常にあいまいな状態となっています。
そのため、労基署の監督官によって判断が分かれるという微妙なことが起こっています。
こんな状態だと、労働者の人数を正しくカウントできません。
そこで、当事務所では各監督官の意見や今までの事例を踏まえて次のように判断しています。
つまり、月に1日でも毎月シフトに入るようなら常時使用としてカウントし、本当に臨時的に入る人はカウントしないという考えです。
厳しい監督官でも上記のカウント方法であれば文句を言わないので、このカウント方法を使用してください。
10名未満なんて無理!とあきらめるのはまだ早い
「確かに週44時間制になると助かるけど、うちの会社はとっくに10人以上いるから使えないよ」
こんな事をよく言われます。
でも、あきらめるのはまだ早い。
まだ活用できる可能性は残っています。
もう一度、条件を確認しましょう。
「上記の業種で常時使用する労働者が10名未満の事業場」
事業場?
会社ではなく、事業場って書いてあります。
実はこの書き方がとても重要で、この事業場というのは会社全体ではなく、飲食業で例えると「独立した一つのお店」の事を言っているのです。
会社が、複数のお店を出店することはよくあることです。
ある店舗で5人の労働者がいて、隣町に新たな店舗をオープンして5名雇ったとしたら、会社全体では10人ですが、事業場(店舗)単位でみるとそれぞれ5人となります。
実は労働基準法は、この事業場(店舗)単位で適用されるのです。
会社全体で10名以上雇用していたとしても、事業場(店舗)単位で人数をカウントして、10名未満だったらその事業場(店舗)では制度を適用できるわけです。
小規模な店舗を複数持っている場合に、それぞれの店舗で週44時間制を導入することができる可能性が残っているのです。
どうやって週44時間制度の活用するの?
2 週44時間を実現する方法
週44時間制を実施する方法としては、次のようなものがあります。
週休1日で、土曜日だけ4時間にする
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 休み | 8時間 | 8時間 | 8時間 | 8時間 | 8時間 | 4時間 |
これで1週間44時間となり、この時間で働いてもらう限りは残業代が発生しません。
週休1日で、1日あたり7時間20分以下にする
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 休み | 7時間20分 | 7時間20分 | 7時間20分 | 7時間20分 | 7時間20分 | 7時間20分 |
これで1週間44時間以内となり、この時間で働いてもらう限りは残業代が発生しません。
別に完全に上記と同じにする必要はありません。このような感じで、週44時間以内であれば曜日ごとに労働時間を設定することができます。
シフト制で1カ月あたりの平均を週44時間以内とする
もっと柔軟に労働時間を決めることはできないのでしょうか?
例えば、曜日ごとに時間を決めるのではなく、1カ月ごとにシフトを組んで働いてもらうなどの方法です。
これができれば小規模店舗では、実際の運用に合っているはずです。
そんな会社に朗報があります。
1カ月単位の変形労働時間制というのを活用すれば、上記のようにシフトを組んで働いてもらうことができます。
そのシフトを組んだ結果、平均して1週間当たり44時間以下になれば残業代は不要です。
具体的には、次の表の労働時間以内でシフトを組めば大丈夫です。
| 対象となる月の暦日数 | 労働時間の総枠 |
| 31日 | 194.8時間 |
| 30日 | 188.5時間 |
| 29日 | 182.2時間 |
| 28日 | 176時間 |
※1カ月単位の変形労働時間制についての詳しい解説はこちらで確認してください。
この方法であれば、1日8時間という枠にとらわれずに、特定の日は9時間労働にすることもできますし、柔軟にシフトを組むことができます。
1ヶ月分のシフトが上記の労働時間の総枠を超えなければ良いわけです。
※補足
- この特例制度を活用しながら、「1カ月単位の変形労働時間制」と「フレックスタイム制」を採用することはできます。
- 「1年単位の変形労働時間制」と「1週間単位の非定型的変形労働時間制」を採用する場合には、週40時間でなければなりません。
- 満18歳未満の年少者にはこの特例は適用されませんので、週40時間以内の労働のみ可能です。
- 変形労働時間制の規定は、満18歳未満の者には適用されません。ただし、満15歳以上満18歳未満の者については1週間48時間、1日8時間を超えない範囲で1カ月単位の変形労働時間制または1年単位の変形労働時間制を適用することができます(労基法60条3項)。